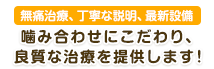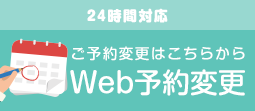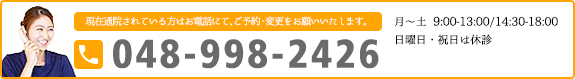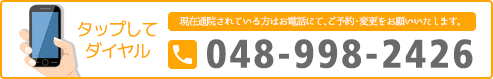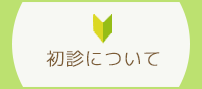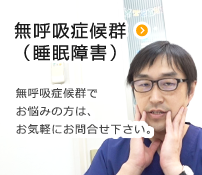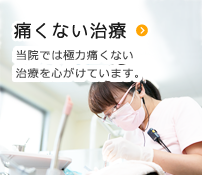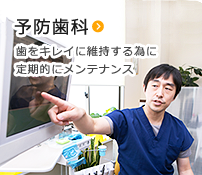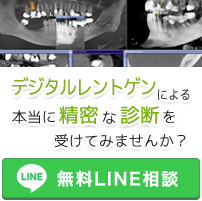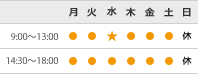埼玉県八潮市のつくばエクスプレス八潮駅前にある歯医者さん、八潮駅前通り歯科医院の院長金田です。
前回咬合調整の際に行う臨床検査について、臨床検査項目は13項目あり全てとても重要とお話しいたしました。
前回のおさらいとなりますが、咬み合わせ調整をする前に超重要13項目は
1主訴問診
2咬合性外傷の診査
3歯列や顎運動異常の診査
4顎関節異常の診査
5Bruxismブラキシズムの診査
6舌や口唇の習癖の診査
7歯の動揺とその診査
8歯の病的移動の診査
9咬耗とその診査
10食片圧入の診査
11打診音の診査
12X線像の診査
13石こう模型による咬合診査
以上の13項目があります。
今回は3~5の項目についてお話します。
3歯列や顎運動異常の診査
下顎の運動は、限界運動と咀嚼や嚥下等の生理的な機能運動とに分けられます。歯列や顎関節、更には咀嚼筋によっても影響を受けます。歯列に関しては、対になる歯を失って突出してくる歯(挺出)や、前歯の交叉咬合などがあると上下の顎運動が阻害されます。
咀嚼や嚥下のような機能運動は、反射によって行われているものですが、嚥下時に片側の歯だけ接触したり、咬みこむときのタイミングやバランスが崩れてくると無意識に接触部位を避けるようになり、顎が右や左にずれた位置で習慣的に咬合するようになってしまいます。下顎の運動を前方、側方から観察し、左右前後のずれを十分に確認します。
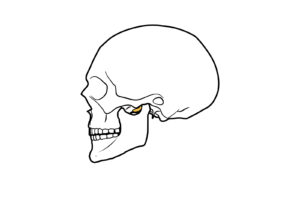
4顎関節異常の診査
症状としては顎運動時の関節の顎関節音(クリッキング音)、顎運動の範囲が制限される、痛み、耳や眼の痛み、頭痛、顔面痛、首や肩のこりや痛みなどが現われます。
X線検査で確認することもありますが、耳や顎関節を直接触診し、顎関節音や運動の円滑さ、左右対称性、タイミングなどを確認します。
5Bruxismブラキシズムの診査
Bruxismブラキシズムとは咀嚼筋の異常な緊張を伴う歯ぎしりで、歯ぎしり、食いしばり、上下の刃をカチカチ咬みあわせるタッピングなどのことです。
そのほか口唇、頬粘膜、下に現われる歯の圧痕もあります。
咀嚼筋群が長時間緊張した状態にあったためにできるものと考えられます。また下顎隅角部の骨が張っている、いわゆるエラが張っていると言われる顎の形も参考となります。歯の浮く感じや顎のだるさ、歯肉のかゆみやチクチク感、首背中腰のこりや痛み、頭痛、目の奥の痛み、顎関節痛についても問診をします。
以上になります。また次回も続きをお話いたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。