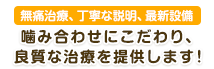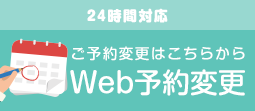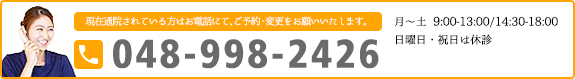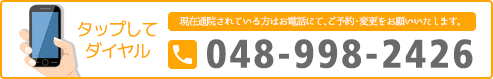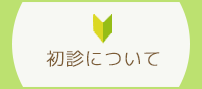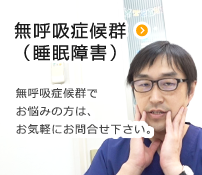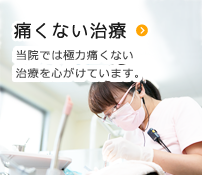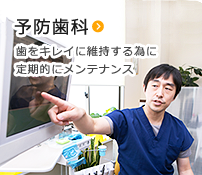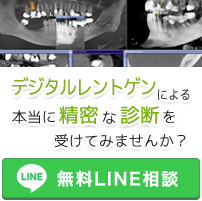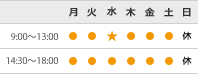埼玉県八潮市のつくばエクスプレス八潮駅前にある歯医者さん、八潮駅前通り歯科医院の院長金田です。
咬合調整の際に行う臨床検査について、臨床検査項目は13項目あり全てとても重要とお話ししています。
おさらいとなりますが、咬み合わせ調整をする前に超重要13項目は
1主訴問診
2咬合性外傷の診査
3歯列や顎運動異常の診査
4顎関節異常の診査
5Bruxismブラキシズムの診査
6舌や口唇の習癖の診査
7歯の動揺とその診査
8歯の病的移動の診査
9咬耗とその診査
10食片圧入の診査
11打診音の診査
12X線像の診査
13石こう模型による咬合診査
以上の13項目があります。
今回は6~8の項目についてお話します。
6舌や口唇の習癖の診査
舌や唇の癖は、歯間離開(歯と歯に隙間が開く)、上顎前突(上の歯が下の歯よりも前に出る)、過蓋咬合(上の歯が下の歯を深く覆いかぶさっている)などと大きく関係します。こういった場合、舌や唇の動きの癖を伴っているので発音や嚥下時の舌や口の動きに注意が必要です。
まず嚥下の診査では、歯のすき間、口が開いてしまっているところに舌を押し付ける癖があるか、舌が前歯に押し付けているか、舌の圧痕からも判断できます。
口唇、唇については、まず唇を閉じたときの口輪筋の緊張度や、顎に梅干状のしわができているかなどを観察します。上顎の前突が進むと、唇を閉じたときに下唇が上顎前歯の先端を覆わずに内側に入ってしまい、唇の外側に歯が出てしまう場合もあります。

7歯の動揺とその診査
咬合性外傷とは強いかみ合わせの力が原因で歯や歯茎、骨などの歯周組織、そして顎関節に損傷を引き起こす状態を指します。歯ぎしりや食いしばり、不正咬合などが原因で起こり、歯の痛みや揺れ、歯茎の炎症、顎関節の痛みなどの症状が現れることがあります。歯の動揺(どのくらいグラグラ動くのか)の増加はその最も重要なひとつとなります。
歯の動揺が増加している場合には必要に応じて咬合状態、顎運動、顎関節、歯や関節のX線写真などを詳しく調べる必要があります。
8歯の病的移動の診査
歯は唇、頬、舌、上下左右に接するお互いの歯の力を受け、支えられて一定の位置に安定しています。しかしこれらの力のバランスが崩れたとき、歯は力の弱い方向へ移動します。
たとえば歯周疾患のある方の上顎前突(上の歯が下の歯よりも前に出る)や歯間離開(歯と歯に隙間が開く)で、口を閉じると下唇をかんだような状態になり、歯が露出していることが見受けられます。このような状態の唇には歯の圧痕があり以前からお同じような状態であったかなど確かめる事もあります。昔の口元が写っている写真などを持参していただき参考にさせていただくこともあります。
今回のお話は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。